中央検査部
中央検査部の組織・業務紹介、検査一覧、スタッフ紹介については、以下のリンクを参照してください。
中央検査部の組織・業務紹介

副理事長 兼 副院長 兼 中央検査部長 兼 研究センター長 兼 臨床研修センター副センター長 兼 感染症内科部長 兼 地域連携部長白木 克哉
中央検査部の理念・業務方針
中央検査部の理念 『私たちは、患者の皆様の立場で迅速、正確な検査結果を提供いたします』
中央検査部の業務方針は以下のとおりです。
- 24時間体制で緊急検査(検体・輸血)を行っています。
- 採血室、病棟より、エアシューターによる輸送を行い効率化をはかっています。
- 早朝早出勤務で、病棟の採血結果および外来診療前検査報告による診療支援
- 病棟採血管準備・外来採血等による看護支援
- ICT,NST,DST等でチーム医療への参画
- 各種認定技師の育成
私たちは、患者さまが安心して検査を受けて頂けるよう、患者さまの立場に立って対応することをこころがけています。
検査一覧
当院で実施している検査(検体検査、生理検査、細菌検査、病理検査)の詳細です。
検体検査
生理検査

生理検査は、主に、脳神経系、呼吸器系、循環器系の検査に分かれており、どれも臨床検査技師がさまざまな検査機器を用い、直接からだの生理的現象を波形や画像として記録する検査です。
脳神経系の検査
脳の電気的な活動の変化を調べたり、運動神経・感覚神経の状態をや筋肉の機能を調べる検査です。
脳波検査、神経伝導検査、大脳誘発電位検査など
自律神経系の検査
自律神経機能の異常等を調べる検査です。交感神経皮膚反応、CV R-R、電子瞳孔検査、重心動揺検査、サーモグラフィなど
呼吸器系の検査
息を吸ったり吐いたりする時の肺や気管・気管支の機能を測定するものです。呼吸器系の疾患のある場合に検査を行いますが、その他にも一般的な手術(全身麻酔)の前や、手術後の回復能力の判定などをみる場合にも行います。
肺活量/努力性肺活量測定、呼吸抵抗測定、呼気一酸化窒素濃度測定、肺機能精密検査(CV・FRC・DLCO)など
循環器系の検査
心臓や血管の機能を調べる検査です。不整脈の有無や心筋梗塞や狭心症などの診断に有用な検査です。
心電図検査、マスター2階段運動負荷試験、トレッドミル運動負荷試験、ホルター心電図検査検査(24時間記録心電図検査)、ホルター血圧心電図検査(日内血圧変動・心電図検査)、血圧脈波検査(CAVI/ABI)など
その他の検査
睡眠時無呼吸症検査(簡易)、サーモグラフィー検査、聴力検査、味覚嗅覚検査、超音波骨密度測定など
細菌検査

細菌検査は、感染症(食中毒、髄膜炎、肺炎など)の疑いがある患者さまの検体(喀痰、尿、便、血液、髄液、膿など)から感染症の原因となる細菌を見つけ、どの薬(抗生物質)が効くのかを調べる検査です。
また、インフルエンザウイルスなどの迅速ウイルス検査や、遺伝子を利用した感染症(新型コロナウイルス・結核・マイコプラズマ)の原因菌を調べる検査も行っています。
病理検査
病理検査の業務は、病理組織検査、迅速組織検査、細胞診検査に分類されます。
また、不幸にしてお亡くなりになられた患者様の病理解剖も行います。
病理検査について詳しくは下記ページをご覧ください。
品質保証施設認証
2014年4月より、当院検査部は日本臨床衛生検査技師会が証明する「品質保証施設認証」を取得しています。(2年ごとに更新)
これは検査データが標準化され、かつ精度が十分保証されていると評価できる施設に対して認証される制度です。
スタッフ紹介
副理事長 兼 副院長 兼 中央検査部長 兼 研究センター長 兼 臨床研修センター副センター長 兼 感染症内科部長 兼 地域連携部長白木 克哉 (シラキ カツヤ) 昭和60年医学部卒業 認定資格 ・日本内科学会認定医/指導医/東海支部評議員、総合内科専門医/指導医 中央検査部副部長 兼 研究センター副センター長和田 英夫 (ワダ ヒデオ) 昭和53年医学部卒業 認定資格 ・日本内科学会認定医 技師長 坂下 文康 (サカシタ フミヤス)

・日本消化器病学会専門医/指導医/学会評議員
・日本肝臓学会専門医/指導医/学会評議員
・日本消化器内視鏡学会専門医/指導医/東海支部評議員
・日本超音波医学会専門医/指導医
・米国消化器病学会フェロー
・米国内科学会フェロー
・インフェクションコントロールドクターICD
・日本医師会認定産業医
・日本臨床検査医学会臨床検査専門医/管理医
・日本感染症学会専門医/指導医
・日本化学療法学会抗菌化学療法認定医
・日本エイズ学会認定医
・三重大学臨床教授
・三重大学連携大学院教授
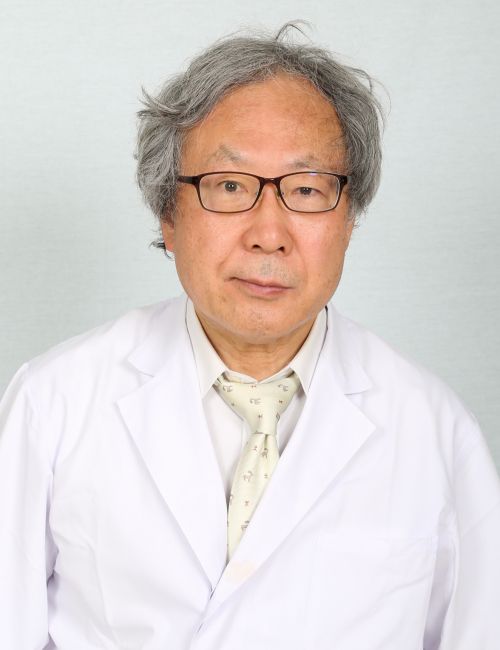
・日本輸血・細胞治療学会認定医
・日本血液学会認定血液専門医
・日本臨床検査医学会臨床検査専門医
・日本老年医学会認定老年病専門医
・日本血栓止血学会認定医
臨床検査技師
- 正規職員:27名
- 非常勤職員:4名
有資格者
- 細胞検査士
- 輸血認定技師
- 栄養サポートチーム(NST)専門療養士
- 日本臨床神経生理学会認定技術師(脳波分野、筋電図・神経伝導分野、術中脳脊髄モニタリング分野)
- 超音波検査士
- 糖尿病療養指導士
- 臨床工学技士
- 心血管インターベンション認定技師
- 認定救急検査技師
- 認定病理検査技師
- 認定心電検査技師
- 認定臨床微生物検査技師
- 感染制御認定臨床微生物検査技師(ICMT)
- 認定認知症領域検査技師








