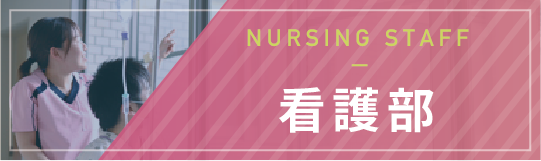診療内容
肺癌
日本における呼吸器外科手術件数は1990年には2万例、2013年では7万例というように一年に2,000例ずつ直線的に増えています。このうち約48%を占める肺癌は喫煙する方の高齢化とともに増えており、加えて、非喫煙者の腺癌も増加の一途をたどっており、肺癌の手術件数は今後も増加が見込まれます。最近では、肺癌手術を受けられる3万数千人の平均年齢は70歳近くとなり、約10%が80歳以上の方々です。
肺癌の治療方針を決定するに当たり、画像診断でその進行度(病期)を判定します。具体的には癌の大きさや周囲臓器への浸潤の有無、リンパ節転移の有無、他臓器への転移の有無等で、11段階の病期(IA1、IA2、IA3、IB、IIA、IIB、IIIA、IIIB、IIIC、IVA、IVB 期)に分かれています。画像診断による病期(臨床病期と言います)IA~IIIAが手術適応となってきます。手術後に実際に切除した肺癌の大きさや、郭清したリンパ節に癌細胞がいるかどうかを調べ、術後の病期(病理病期と言います)を判定します。
2004年に切除された肺癌症例についての全国集計が2010年に行なわれましたが、参加施設数は呼吸器外科専門医修練認定施設605施設中253施設(41.8%)で、症例数は11,663例でした。病期関係なしの全体の5年生存率は69.6%で、そのうち男性の5年生存率は63.0%、女性では80.9%でした。尚、病理病期別の5年生存率は、IA期:86.8%、IB期:73.9%、IIA期:61.6%、IIB期:49.8%、IIIA期:40.9%、IIIB期:27.8%、IV期:27.9%でした。
肺癌の標準手術は癌のある肺葉(人間の肺は、右は3つの肺葉、左は2つの肺葉に分かれています)の切除と、癌の転移経路であるリンパ節を切除(郭清)することです。
一方で近年、CT等の画像診断装置の進歩により肺の末梢に存在する小さい肺癌が発見される頻度が増加してきました。これらの末梢小型肺癌に対しては肺の切除範囲を小さくしても(区域切除:癌病巣を肺葉がさらに細かく区画された区域単位で切除する)予後が変らないという報告がみられるようになってきました。肺の切除範囲が少なければ少ないほど呼吸機能が温存されるため、当科でも2cm以下の末梢小型肺癌に対しては、患者さんの同意を得たうえで区域切除を積極的に行っております。
気胸
気胸の手術は、日本では1年間に約13,000人に行われています。気胸は若い男性に多く見られる病気ですが、高齢化社会とともに高齢者の気胸も確実に増加しているのが現状です。高齢者の気胸は肺気腫、間質性肺炎などの合併症が多く難治性のものが多いのが特徴です。当科では早期の社会復帰ができるように努めております。
炎症性肺疾患、膿胸
当科では近隣のかかりつけの医院、近隣の総合病院と連携し膿胸の手術を積極的に行っており良好な成績を各学会でも発表しております。膿胸の患者さんは体力が低下している方が多く患者さんのQOL(生活の質)が保てるような手術を行うよう努めています。
手術の傷について
手術のアプローチ方法には開胸手術と胸腔鏡手術があります。開胸手術の利点は直視下に質の高い手術が行えることにありますが、手術創(からだに残る傷痕)がやや大きくなるという欠点があります。また、開胸器にて肋骨と肋骨の間を開大するため痛みも大きくなります。胸腔鏡手術では手術創が小さく痛みが少ない利点がある半面、急に出血した場合の対処が不十分といった欠点を指摘されています。当科では癌の根治性と手術の安全性を確保するために、12cm前後の皮膚切開創で行う開胸手術を標準術式としてきましたが、胸腔鏡手技の習熟に伴い2009年から創のサイズを縮小し、現在では5cm程度の切開創での胸腔鏡下手術を中心に行っております。
ロボット支援下手術について
2018年4月より、肺悪性腫瘍(肺癌、転移性肺腫瘍)に対する肺葉切除術、および縦隔腫瘍手術に対し、基準を満たした施設においてロボット支援下手術を行うことが可能となりました。
これを受けて、2019年5月に手術支援ロボット(ダヴィンチ)を三重県下北勢地区で初めて導入し、通算10症例のロボット支援下の肺切除術を経験しましたので、当院でも保険診療で行うことが可能となりました。
ロボット支援下手術では、術者が3D画像を見ながら手術操作できる点、胸腔内で自由度の高い関節のある鉗子を使用できる点、手ぶれが全く無い点などで優れております。また、手術の傷がほぼ同一肋間に限局していることから術後疼痛軽減のメリットもあります。
当科では、胸腔鏡下手術の経験により培った技術を基に、より繊細な手術操作が可能、かつ低侵襲であるロボット支援下手術を2019年11月から開始しました。安全第一とし適応症例に対しては今後も積極的に進めて参りたいと思います。